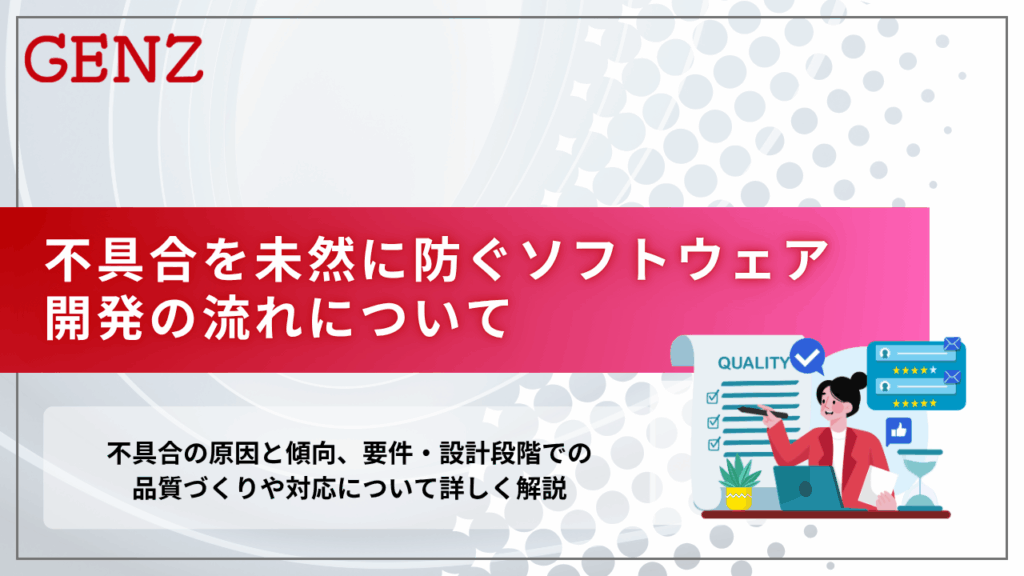
目次
不具合の原因と傾向
■不具合の主な原因カテゴリ
・要求・要件の不備
・設計ミス
・実装ミス、コーディングミス
・テスト設計、実行の不備
・環境や依存関係の違い
・変更対応時のデグレード
■要求・要件定義でのミスが大きな不具合につながる
・どのような影響があるか
・どのようなリスクがあるか
要件・設計段階での品質づくり
■要件とコスト・納期のバランスを意識する
■あいまいな表現はそのままにしない
■例外的な操作や異常時の対応を設計に含める
■レビュー体制の整備
テスト設計と実行での不具合予防
■テスト設計時の観点と技法
・同値分割・境界値分析・状態遷移テストなどの網羅的設計
・リスクベースドテストで優先度を決めて効率化
■自動テストと手動テストの使い分け
・単体レベルでは自動化、UIや複雑な動作確認は手動で
・修正時にはリグレッションテストで副作用をチェック
■テスト環境の整備
・本番環境との違いがバグ原因に
・モックやテストデータの本番近似化が重要
不具合が出たときの対応と学びの仕組み
■なぜ起きたのかを深く調べる
■不具合の情報をチームで共有する
■ふりかえりで次の開発に活かす
はじめに
ソフトウェア開発において、不具合(バグ)の完全なゼロを実現することは困難です。
どれほど経験を積んだエンジニアがプロジェクトを担当していても、仕様の漏れや設計ミス、テストの不足など、さまざまな要因によって不具合は発生します。
そして、それがリリース後に発覚すれば、ユーザーの信頼を損ねるだけでなく、企業にとって大きな損失や信用問題へと発展する可能性もあります。
特に金融・医療系のシステムでの不具合は社会的な影響が大きく、十分な注意を払わなければなりません。
こうした背景から、近年では「不具合を後で直す」こと以上に、「不具合を最初から作り込まない」ことが重要視されるようになっています。
すなわち、品質はテストの段階で担保するのではなく、要求定義、もしくは、要件定義や設計といった上流工程から一貫して作り込むべきものなのです。
ソフトウェア開発の上流工程と下流工程の両方で不具合が作りこまれないように、また、不具合を効率よく発見できるようにしていく仕組みが必要になってきます。
本記事では、不具合の主な原因とその傾向を明らかにしたうえで、開発プロセスの各段階においてどのような工夫や取り組みが不具合の予防につながるのかを紹介します。
「発生を前提とした対処」ではなく、「未然に防ぐための仕組みづくり」へと視点を切り替えることで、より信頼性の高いソフトウェア開発を実現することができます。
不具合の原因と傾向
ソフトウェアの不具合は、必ずしも「開発者のうっかりミス」によって起こるわけではありません。
むしろ、不具合の多くは、プロジェクトの初期段階での認識のズレや設計上の見落とし、運用環境とのギャップといった、複数の要因が複雑に絡み合って生まれます。
ここでは、ソフトウェア不具合の代表的な原因と、上流工程でのミスがプロジェクト全体にどのような影響やリスクを与えるかについて紹介します。
■不具合の主な原因
以下では、不具合の主な原因を順番にあげて説明していきます。紹介するものは以下の6つです。
- 要求・要件の不備
- 設計ミス
- 実装ミス、コーディングミス
- テスト設計、実行の不備
- 環境や依存関係の違い
- 変更対応時のデグレード
要求・要件の不備
最も根本的な原因のひとつが、要求や要件の不明確さです。
たとえば、「ユーザーが使いやすい画面にする」といった曖昧な表現では、開発者と依頼者の間で解釈が異なる可能性が高く、出来上がった機能が期待に沿わないことがあります。
また、そもそも不要な機能が要件に含まれていたり、必要なセキュリティ要件が抜け落ちていたりするケースもあります。
設計ミス
設計段階でのロジックの見落としや仕様の甘さも、不具合の原因となります。
特に注意しておきたいのは、例外処理やエラー時の挙動、境界値付近の動作などです。非正常系のシナリオを十分に検討していない場合、想定外の入力や利用方法で簡単に問題が発生してしまうことがあります。
実装ミス、コーディングミス
ロジックの間違いや条件文の記述ミス、変数の扱いの誤りなど、プログラムの書き方そのものによる不具合もあります。
自動化されたツールやコードレビューによってある程度は検出可能ですが、複雑な処理ではミスが紛れ込みやすくなります。
テスト設計、実行の不備
必要なテスト観点が漏れていたり、テストケースが不十分であるとき、または十分な検証時間が確保されなかったことによって、不具合が見逃されることがあります。
特に「仕様通りに動くこと」ばかりに目が向き、「仕様が間違っている可能性」まで踏み込んだテストが行われないと、本質的な欠陥は見つけにくくなります。
このように、要求定義、要件定義の段階での認識のズレや、顧客の要望の不理解はのちのちの工程に大きな影響を及ぼしかねません。
環境や依存関係の違い
テスト環境と本番環境の設定の違い、OS・ブラウザの違い、外部APIの挙動変更など、環境に依存する問題も無視できません。
開発段階では正常に動いていたにもかかわらず、本番環境でのみ不具合が再現するというケースもよくあります。
変更対応時のデグレード
既存機能に手を加えた際に、別の部分に影響を及ぼしてしまう「デグレード」も典型的な不具合の原因です。
変更の影響範囲を過小評価してしまうことで、思わぬ機能が壊れてしまうリスクもあります。
■ 要求・要件定義でのミスが大きな不具合につながる
不具合は、プログラム実装やテスト工程だけでなく、要件定義や設計といった上流工程での判断や作業に起因することが少なくありません。
そして、上流での小さな判断ミスや認識のズレが、下流工程で大きな影響を及ぼし、修正にも多大な工数とコストがかかることがあります。
ここでは、上流工程でのミスが、どのようにプロジェクト全体に影響を及ぼすのか、どのようなリスクを生じさせるのかについて紹介していきます。
どのような影響があるか
たとえば、要件定義の段階で「どのようなユーザーが、どの場面でこの機能を使うのか」といった利用シーンの理解が不十分なまま開発が進んでしまうと、実際の利用場面に適さない仕様がそのまま設計・実装されてしまいます。
このような場合、機能そのものは正しく動いていても、ユーザーにとって「使いにくい」「想定と違う」と感じられてしまい、後になって仕様変更が必要になることがあります。
こうした修正は、見た目上のUI変更だけで済むことは稀で、ロジックやデータ構造、時には他機能との連携の見直しが必要になるため、下流工程での修正負担が急激に増大します。しかも、すでに作成されたテストケースやドキュメントも見直す必要が生じ、開発全体への影響が広がります。
どのようなリスクがあるか
実務上、多くの不具合はプログラムの書き間違いよりも、そもそもの「仕様の誤解」や「前提条件の抜け」によって生じています。
たとえば、「操作を中断したときは前の状態に戻す」といった曖昧な記述が要件定義に含まれていた場合、それをどう設計・実装するかは開発者の解釈に委ねられてしまいがちです。
こうした曖昧な部分がそのまま設計に反映され、結果として「思っていた動きと違う」といったクレームや修正依頼が発生します。
また、設計段階で「異常系」や「境界値」といった想定外の利用パターンが検討されていないと、リリース後にユーザーが想定外の操作をした際、クラッシュや不具合に繋がる恐れがあります。
設計の穴はテストでも見つけにくく、見逃されたまま本番環境に持ち込まれるリスクが高いため、非常に厄介です。
小さな見落としが重大なインシデントを招いてしまうことがあります。
たとえば、Webサービスにおけるログイン機能の実装で、「ログイン失敗時にエラーメッセージを表示する」という要件は一見簡単に見えます。
しかし、表示するエラー内容に「入力したメールアドレスが存在しません」と記載した場合、これは第三者によるアカウント情報の推測を助けるセキュリティリスクとなります。
このような見落としは、要件段階でセキュリティ面の考慮がなされていなかったことが原因であり、結果として情報漏洩リスクという重大インシデントを招く可能性があります。
同様に、「バッチ処理を毎日自動で実行する」という仕様において、何らかの障害で失敗した場合のリトライ設計や通知フローが検討されていないと、データ欠損や業務停止が発生してしまう恐れもあります。
こうした小さな前提の見落としが、本番環境での事故や運用トラブルに直結してしまいます。
要件・設計段階での品質づくり
ソフトウェアの不具合を防ぐには、開発のはじまりである「要件定義」や「設計」の段階で、しっかりと土台をつくることがとても大切です。この章では、要件や設計を進めるときに気をつけたい4つのポイントを紹介します。
■要件とコスト・納期のバランスを意識する
要件定義では、「何を作るか」だけでなく、それを「どのくらいのコストと時間で作るか」というバランス(QCD:品質・コスト・納期)も一緒に考える必要があります。
たとえば、すべての要望を叶えようとすると、開発期間が長くなり、コストもふくらんでしまいます。逆に、短期間・低コストを優先しすぎると、検討不足のまま進めてしまい、あとで手戻りや不具合が起きやすくなります。
このような事態を避けるには、「必要な機能にしぼる」「段階的にリリースする」といった判断が必要です。非機能要件(例:セキュリティやレスポンス速度など)も早い段階で整理し、関係者で合意をとっておくことが重要です。
■あいまいな表現はそのままにしない
要件定義の際にでてくる、「便利に使えるようにしたい」「わかりやすい画面にしてほしい」といったあいまいな言葉には気を付けましょう。
このような言葉は、人によって解釈が異なるため、あとで「思っていたのと違う」といったトラブルにつながることがあります。
これを防ぐためには、要望をできるだけ具体的な表現に置き換えることが大切です。
たとえば、「検索結果は1秒以内に表示」「1ページに最大5件表示」といったように、確認可能な形に直すことで、開発者・テスター・依頼者のあいだで共通の理解を持つことができます。
また、要件定義の段階から関係者と何度も話し合いを重ねて、「どういう動きを期待しているのか」「どこまでが最低限必要か」など、期待値をすり合わせていくことが、後戻りの少ない開発につながります。
■例外的な操作や異常時の対応を設計に含める
設計を行うときには、「正しい使い方をしたとき」だけでなく、「想定外の使い方をされたとき」や「異常が起きたとき」なども考えておく必要があります。
つまり、エラーや境界値付近での動きについて事前に考慮しておきましょう。
たとえば、ネットが切れたときの動きはどうするか、入力ミスや不正な値が来たときにどう表示するか、データが0件や最大件数だったときにどう処理するか、といったことです。
このようなエラーや境界のケースについてあらかじめ対応方法を設計しておくなら、思わぬトラブルを未然に防げます。
これらを後から追加しようとすると、設計やコードの大きな見直しが必要になり、手間やコストがかかります。
だからこそ、最初の段階から異常時の動きや例外パターンを洗い出し、設計に組み込んでおくことが重要となります。
■レビュー体制の整備
どれだけ注意して設計や要件を作成しても、人間である以上、ミスや抜け漏れは避けられません。
そこで必要になるのがレビュー体制の整備です。
レビューでは、次のような観点からチェックを行うのが効果的です:
- 業務として正しい内容になっているか
- 実装できる内容になっているか
- テストで確認できるように書かれているか
- セキュリティ・性能・使いやすさなどに問題はないか
こうした多面的なチェックを行うには、設計者だけでなく、開発者、テスト担当者、場合によっては運用チームなど、いろいろな立場の人が参加することが望ましいです。
また、レビューの記録をきちんと残しておくことで、あとから変更があったときの確認にも使えますし、他のメンバーへの引き継ぎ資料にもなります。
テスト設計と実行での不具合予防
ソフトウェア開発における不具合を防ぐうえで、テストは非常に重要な役割を担います。
テストは単なる確認作業ではなく、設計の妥当性や実装の正しさを検証し、潜在的なリスクを早期に発見するための「品質保証活動」です。
この章では、不具合の発生を最小限に抑えるために、テスト設計・実行において特に意識すべき3つの視点について解説します。
■テスト設計時の観点と技法
同値分割・境界値分析・状態遷移テストなどの網羅的設計
効果的なテストを実施するには、まず設計段階で「どのような観点からテストを行うか」を明確にする必要があります。
ここで重要になるのが、テスト設計技法の活用です。さまざまな技法を適切に組み合わせることで、抜けや漏れの少ないテスト設計が可能になります。
たとえば、同値分割では、似たような入力値をグループに分け、代表値だけをテストすることで効率的な設計ができます。
境界値分析は、エラーが起こりやすい最大値や最小値、閾値付近を重点的に確認する手法で、数値入力や範囲条件を扱う場合に特に有効です。
また、状態遷移テストでは、画面やステータスの変化を整理し、状態ごとの動作が正しく行われるかを確認します。
ログイン・ログアウトやステータス変更など、操作の順序が影響する処理に向いています。
さらに、デシジョンテーブルテストも非常に有用な手法です。これは複数の条件が組み合わさって異なる結果を生む処理に対して、条件と対応する結果を表形式で整理し、すべての組み合わせを網羅的に確認するためのものです。
割引計算や権限チェックのように、「条件が増えると正誤の組み合わせも増える」ようなロジックでは、仕様の漏れや矛盾を事前に発見しやすくなります。
このような技法を活用してテストケースを設計することで、開発者やテスト担当者が「どこをどう確認すべきか」を共通の視点で捉えられるようになり、仕様の曖昧さにも気付きやすくなります。
リスクベースドテストで優先度を決めて効率化
限られた時間や工数のなかで効率的にテストを行うには、リスクに基づいた優先順位づけが有効です。
リスクベースドテストでは、ユーザーに影響を与えやすい機能や、過去に不具合が多く見つかった領域を重点的にテストする一方で、影響の小さい箇所は簡易的に留めるなど、効果とコストのバランスを取る工夫がなされます。
重要度の高い部分を確実にカバーすることで、限られたリソースの中でも高い品質を実現できます。
■自動テストと手動テストの使い分け
テストの実行方法には、大きく分けて「手動テスト」と「自動テスト」があります。
どちらにも強みと弱みがあるため、テスト対象や目的に応じて適切に使い分けることが求められます。
単体レベルでは自動化、UIや複雑な動作確認は手動で
「手動テスト」は、UI(ユーザーインターフェース)の使い勝手や画面表示のバランス、複雑な操作の組み合わせなど、人の感覚が関わる部分で強みを発揮します。
一方、ソースコードの関数単位での確認や、処理結果の一貫性を継続的に検証するような場面では、「自動テスト」が適しているといえます。
自動化することで人為的なミスを防ぎつつ、短時間で繰り返しテストを実施できるため、品質を安定させる効果が期待できます。
修正時にはリグレッションテストで副作用をチェック
ソフトウェア開発の修正時には必ずリグレッションテストを実施しましょう。
開発後半やリリース直前に見落とされがちですが、機能修正や改善対応の際には「デグレ(他の機能への影響)」が発生しがちです。
リグレッションテストは、修正箇所だけでなく、その周辺や関連する既存機能が問題なく動作するかを再確認するテストであり、プロジェクト全体の品質を守るための「保険」のような役割を果たします。
特に、アジャイル開発のように短いサイクルで継続的に機能追加・変更が行われる場合、リグレッションテストの実施が習慣化されていなければ、気付かぬうちに品質が低下してしまうリスクがあります。
そこで、あらかじめよく使われる機能やクリティカルな処理については自動テストとして仕組み化しておくと、修正のたびに効率的かつ確実にリグレッションを実施できるようになります。
■テスト環境の整備
本番環境との違いがバグ原因に
テストを行う「環境」も、品質を左右する重要な要素の一つです。
本番環境とテスト環境の構成や設定が異なっていたために、テストでは正常だったのにリリース後に不具合が発生するという事例は少なくありません。
たとえば、サーバーのタイムゾーン、データベースの設定、外部連携先の仕様の違いなど、細かな差異が予期せぬトラブルを引き起こすことがあります。
モックやテストデータの本番近似化が重要
上記のようなリスクを避けるため、テスト環境と本番環境を近づけることが必要になってきます。
外部サービスや他システムと連携する部分については、モック(仮の代替機能)を活用して動作を再現したり、実データに近い形のテストデータを使って検証したりすることで、実運用に近い状態でのテストが可能になります。
また、環境構築の手順をドキュメント化し、誰が見ても同じ環境が再現できる状態にすることも、安定したテスト品質を保つために重要です。
不具合が出たときの対応と学びの仕組み
どれだけテストや設計に力を入れても、ソフトウェアの不具合を完全にゼロにすることは困難です。
大切なのは、不具合が発生したときに「ただ修正する」だけでなく、なぜ起きたのか、どうすれば再発を防げるのかを考え、チームや組織として知見を蓄積していくことです。
ここでは、不具合が出たときの対応とそこからの学びを以下の3ステップに分けて紹介します。
■なぜ起きたのかを深く調べる
不具合が発生したとき、まず最初に行うべきは原因の特定です。
ただし表面的な「〇〇の処理が間違っていた」といった指摘にとどまらず、本質的な原因(根本原因)を探ることが重要です。
たとえば、入力チェックが漏れていたという不具合に対して、それを「チェック処理を忘れていた」とするだけでは対策が不十分です。なぜ忘れていたのか、なぜレビューで見つからなかったのか、といった背景まで掘り下げる必要があります。
そのために有効な手法として、「5Whys(なぜを5回繰り返す)」があります。
これは「なぜそのバグが起きたのか?」を繰り返し問い、徐々に原因を深掘りしていくアプローチです。
また、フィッシュボーン(特性要因図)のように、要因を「人」「方法」「ツール」「環境」などのカテゴリで整理しながら原因を分析する方法もあります。
このような分析を通じて、単なるコードの修正にとどまらず、設計方針、開発手順、レビュー体制などの課題にも目を向けることができます。
■不具合の情報をチームで共有する
不具合が起きたときの情報を、その場限りで終わらせず、組織のナレッジとして蓄積・共有していくことも重要です。
まず、不具合の管理には、チケット管理ツール(例:JIRA、Redmine、Backlogなど)を使って、発生内容、再現手順、修正方法、リリース状況などを記録するのが基本です。
これにより、過去にどんな不具合があり、どのように対応したかを後から追跡できるようになります。
また、単なる記録にとどまらず、定期的な不具合共有会や品質レビュー会を設けて、発見された課題をチーム全体に共有することが効果的です。
たとえば、「このような思い込みがバグにつながった」「設計段階でこれを見ていれば防げた」といった具体的な気づきを全員で共有することで、似たようなミスの再発防止に役立ちます。
さらに、よくある失敗や教訓をナレッジベース化しておけば、新しく入ったメンバーや他のプロジェクトにも知見を展開できます。
不具合を起点に組織全体の学習が進むような仕組みを持つことが、不具合対応を「資産化」するうえで鍵となります。
■ふりかえりで次の開発に活かす
不具合対応を一時的な対処で終わらせず、次のプロジェクトや今後の開発活動に活かす仕組みを持つことも欠かせません。
その中心となるのが、定期的なふりかえりミーティング(レトロスペクティブ)です。
ふりかえりでは、不具合の原因だけでなく、「プロジェクトのどこに改善の余地があったか」「どのプロセスがうまくいったか・いかなかったか」など、開発全体のプロセスに目を向けて議論します。たとえば、「レビュー観点が不足していた」「テスト観点の漏れがあった」などの気づきがあれば、それを今後の標準プロセスやテンプレートに反映することで、仕組みとして品質を高めていくことができます。
また、ふりかえりは単なる反省会ではなく、改善と再発防止に向けた具体策をチームで合意する場でもあります。
「次回はレビューシートを改訂する」「設計ドキュメントのテンプレートを見直す」といったアクションを明確にすることで、ふりかえりが形骸化せず、実効性を伴った改善活動につながります。
このように、ふりかえりを通じて開発プロセスを継続的に改善する姿勢を持つことが、不具合を減らし、チームの品質意識を高める重要な一歩になります。
まとめ
ソフトウェア開発では、どんなにテストしても不具合がゼロになることはなかなかありません。
よくある原因には、そもそもの仕様のあいまいさ、修正による他への影響の見落とし、テスト設計の甘さや環境の違いなどがあります。
特に、仕様書にモレや曖昧な表現があると、肝心のテストでチェックしきれず、気づかないままリリースされてしまう…ということも起こります。
そうした事態を防ぐには、まずは仕様をレビューでしっかり確認すること。
そして、「この修正が他にどう影響するか?」を開発チームで共有したり、テスト技法(同値分割や境界値分析、デシジョンテーブルなど)を使って抜けのないテスト設計を行うのがポイントです。
また、本番に近い環境でテストすることや、修正後のリグレッションテスト(再確認)も欠かせません。
また「顧客と開発者の認識のズレ」は初期不具合の大きな原因となります。
要望がふんわりしていたら、きちんと話し合い、共通の認識をもてるように努めましょう。
