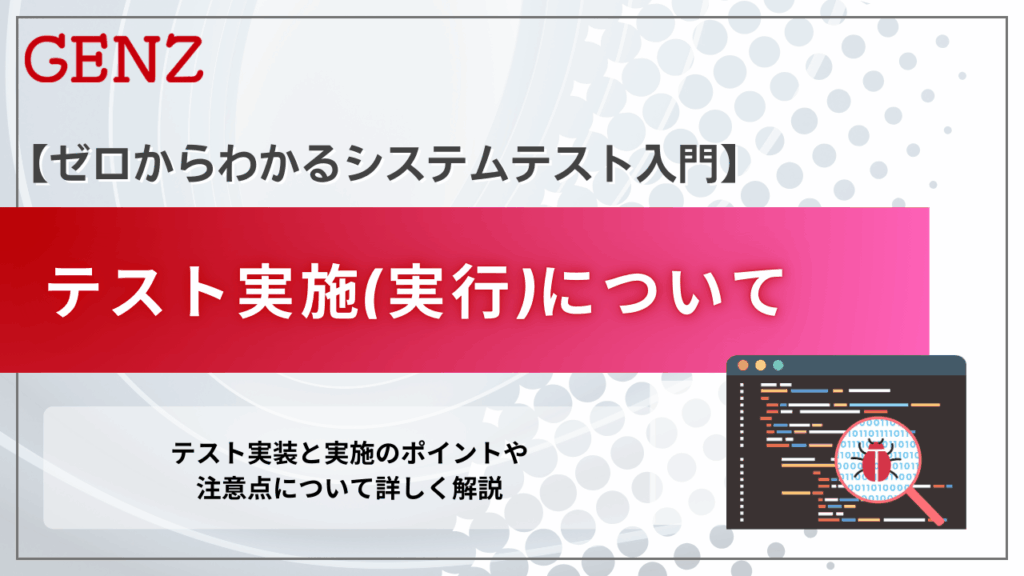
ソフトウェア開発において「テスト」は欠かせません。ですが、そのテストを「どのように進めていくか?」を明確にしておかないと、品質もスケジュールもバラバラになります。ここで重要になるのが「テスト戦略」です。今回は「テスト戦略」について紹介していきます。
テスト戦略とは
■テスト戦略の定義
テスト戦略とは、一言で言えば「品質を守るための、テスト全体の指針」です。もっとわかりやすく例えるなら、「どの山に登るか」「どういうルートで行くか」を決める登山計画のようなものです。
具体的にいえば、
- どんな品質リスクがあるか?
- どこに重点的にテストを行うか?
- 手動テストと自動テストのバランスはどうするか?
- 開発サイクルにどう組み込むか?
といった、なぜそのテストが必要になるのか、どこに重点を置くべきか、ということを定めるのがテスト戦略です。策定される時期としてはプロジェクトの初期となります。
■なぜテスト戦略が必要か
現代のIT業界は、日々めまぐるしく進化しています。
技術革新のスピードは年々加速しており、クラウド技術やテスト自動化ツールの登場によって、ソフトウェア開発の在り方も大きく変わりました。
また、ユーザーの期待は非常に高く、サービスに求められる品質基準も厳しくなっています。このような状況に対応するため、開発のスピードを落とさずに高品質なソフトウェアをリリースし続けることが企業にとっての大きな課題となっています。
アジャイル開発やDevOpsといった手法の普及により、開発とリリースのサイクルは短縮され、ソフトウェアはより早く市場に投入されるようになりました。しかし、このスピード感の中でテストを後回しにしたり、場当たり的に進めたりしていては、品質が犠牲になりかねません。
こうした課題に対処するためにはテスト戦略が欠かせません。テスト戦略が存在しない場合、テストの優先順位が不明確になり、重要な部分の検証が漏れてしまうことがあります。
逆に、必要以上に細かい部分に時間を費やしてしまい、リリースの遅延を招くケースも見受けられます。また、どの工程を自動化するかといった判断が曖昧なままだと、メンテナンス性の低い自動テストが乱立し、かえって手間やコストが増大することにもなりかねません。
特に、複数のチームが関与する場合には、テスト戦略がなければ深刻な問題を引き起こします。チーム間でテストの方針や基準が異なれば、テスト範囲に重複や漏れが生じやすくなり、不具合の発見や修正が後手に回るリスクも高まります。
■テスト計画とは
テスト計画とは、テスト戦略をもとにした「実行のための計画書」といえます。テスト戦略が「登山のルート選び」だとしたら、テスト計画はその登山に必要な「持ち物リストと日程表」です。それで、テスト計画には、具体的に、いつ、だれが、何をつかってテストするのかという情報が記載されます。例えば以下のような情報です。
- 何をテストするのか(スコープ)
- いつ・誰が・どこでテストするのか(スケジュール・担当者)
- どうやって管理するのか(進捗・品質の評価方法)
- 使用する環境やツール
- テストの終了基準
つまり、戦略を現場で実行するための具体的なプランがテスト計画なのです。
しかし、テスト計画が行われているからといって品質が保証されるわけではありません。特に、過去の社内標準サンプルや過去のテスト計画の使いまわしであったりすると、現状の課題を解決し、あるべき姿に近づけようとするテスト戦略とかみ合わず、計画通りにテストが実行できない事態になりかねません。
テスト戦略で定められた施策を、どのようにすれば実現できるのか、与えられた工数をどのように使えば最大限の効果が得られるのかということを明文化するのがテスト計画の役目です。テスト計画はテスト戦略より下位におかれるものですが、与えられた工数や制約条件を検討した結果、テスト戦略そのものを見直すというケースもありえます。テスト戦略とテスト計画はセットでなりたっていると覚えておきましょう。
■全体テスト計画と個別テスト計画
テスト計画には、対象となる範囲の違いで2種類が存在します。全体テスト計画と個別テスト計画です。全体テスト計画は、プロジェクト全体に関わる計画であり、全体のテスト方針・体制・進め方などを記載します。一方、個別テスト計画は、特定のレベルやフェーズに限定したテスト計画で、具体的なテスト内容や実施方法を細かく記述します。全体テスト計画が木の幹であれば、個別テスト計画は木の枝葉だといえます。当然ですが、全体テスト計画が策定されてから個別テスト計画が策定されます。
テスト戦略の内容によって、これらの2種類のテスト計画は影響をうけることになります。例えば、あるテストレベルを強化することがテスト戦略で決まれば、全体テスト計画で、各テストレベルの実施基準を見直して工数を調整する必要があります。
単純にテストケース数を増減するだけではなく、機能に優先度をつけてテストケースの最適配分を考えることもあるでしょう。また、新しいツールや開発体制の導入など、新たな取り組みを導入することもあるでしょう。このような場合は全体テスト計画で大方針を示すのはもちろんのこと、個別テスト計画においては、対象テストの範囲や具体的な運用手順、ツールの導入時期、学習スケジュール、試行の要否などを細かく計画する必要があります。
■テスト戦略とテスト計画の関係性
以上のようにテスト戦略とテスト計画は密接に関わっています。両者について簡単にまとめたものが下の表になります。
| 種別 | 目的 | 内容 | タイミング |
|---|---|---|---|
| テスト戦略 | 「なぜ・どこに・どうやって」テストを行うかという全体方針 | リスク評価、テストタイプ選定、優先順位付け | プロジェクト初期(要件定義~設計初期) |
| テスト計画 | テスト戦略をもとにした実行可能な計画 | スケジュール、リソース、テスト項目、環境 | 各開発フェーズの直前または中盤 |
テスト戦略のたて方
ソフトウェア開発におけるテスト戦略の策定は、単にテスト手法を選ぶだけではなく、プロジェクト全体の成功に向けた土台づくりであり、戦略的な意思決定の連続です。この部分では、テスト戦略を立てるうえで重要な4つのステップを紹介します。
■組織やプロジェクトのあるべき姿を明確にする
テスト戦略の第一歩は、組織やプロジェクトが中長期的に目指す「あるべき姿」を明確にすることです。これは、単に今回の開発に限らず、将来的にどのような品質レベルを目指すのか、開発プロセスや管理手法をどう進化させていくのかといったビジョンを描くフェーズです。
たとえば、リリース後のバグをゼロに近づけたい、リグレッションテストの自動化を進めて工数を削減したい、あるいはアジャイル開発への移行を推進したいなど、組織全体の変革も含めた長期的な展望を共有し、関係者間で合意を形成することが求められます。ここでのビジョンは、テスト戦略の方向性を決定づける重要な基盤となります。
■今回のプロジェクトの目標を明確にする
将来のあるべき姿が明らかになったら、その理想に向けて、今回のプロジェクトでどこまで到達するかを具体的に定める必要があります。このとき大切なのは、現状と将来像とのギャップを正しく把握し、それをどう埋めていくかという視点を持つことです。現状の延長だけでは到達できない場合には、大きな発想の転換や技術的なブレイクスルーも求められるかもしれません。
プロジェクト毎にたてられるテスト戦略の場合、組織やプロジェクトのあるべき姿を明確にするステップからではなく、ここで説明するプロジェクトの目標を明確にすることからスタートします。
また、目標を考える際には、一つの視点に偏らないことも重要です。たとえば、バグが多いからといって単にテストの量を増やすだけではなく、コードの書き方やレビュー体制に問題がないか、開発プロセス全体を広い視野で見直す必要があります。多面的な観点から問題をとらえることで、より本質的な改善が可能になります。
さらに、すべてを一度にやろうとするのではなく、「やらないこと」を決めることも重要です。プロジェクトで実現したいことは数多くありますが、すべてを一度に詰め込んでしまうと無理が生じ、かえって成果が中途半端になりがちです。
今回はあくまで将来像に近づくための段階の一つと位置づけ、現実的な到達目標を設定するようにしましょう。たとえば「法改正への対応を優先する」といった、期限や外部要因によって左右される目標がある場合は、それも合わせて明確にしておきます。
こうした検討を踏まえ、プロジェクトの目的と、目指す到達点をチーム全体で共有することが、戦略立案の土台となります。
■目標を実現するための基本戦略を策定し、テストアプローチを決定する
プロジェクトの目標が明確になったら、それを実現するためにどのような戦略を取るべきかを具体的に検討します。テストの方針(アプローチ)を決めることで、リソースの使い方や実施すべき施策が見えてきます。
たとえば、「バグを減らすこと」が目標であれば、まず現状のバグの傾向を分析します。バグがどの工程で多く入り込んでいるのか、どのテストレベルで見逃されやすいのかといったデータをもとに、レビューの質を上げるべきか、特定のテスト工程を強化すべきかを判断します。その上で、工数の問題なのか、やり方に課題があるのかを切り分け、対応策を考えていきます。
「リグレッションテストの効率化」が目標であれば、自動化の検討が有力な選択肢になります。ただし、どの範囲(単体テストなのか統合テストなのか)を自動化するのが効果的なのか、使用するツールの選定や、導入に必要なスキルをチームが持っているかどうか、社内で進められるのか外部の支援が必要なのか、といった実行可能性も合わせて検討する必要があります。
また、「テストの実行管理を効率化したい」といった目標に対しては、進捗管理やバグ報告などの業務にどれだけ工数がかかっているか、現行の管理指標やチェック体制が適切かといった観点から現状を評価し、自動化できるポイントを見つけていきます。
このように、目標を達成するための手段は1つではなく、状況によってさまざまです。たとえば、リスクが大きい部分に集中して対応したいなら「リスク分析に基づくアプローチ」、限られた経験や資料から推測しながら進めるなら「経験ベースのアプローチ」、あらかじめ決められた仕様に沿って着実に進めるなら「規定ベースのアプローチ」といった選択肢があります。
重要なのは、目標と現実のギャップを冷静に見極め、効果と実現可能性のバランスを取りながら、最も適した施策を選び取ることです。ここで決まったテストアプローチが、以降の戦略立案とリソース配分の軸となります。
■個別戦略を策定し、リソースの投資配分を決める
基本戦略が定まったら、それを具体的に各テスト対象に適用するための「個別戦略」を策定します。個別戦略では、画面単位や機能単位、テストレベル(単体・結合・システム)ごとに適切なテスト技法やツールの選定、担当者の割り当てなどを細かく決定していきます。
また、新しい施策を導入する際には、限られた工数や予算のなかでどこにどれだけ投資するかを明確にすることも重要です。たとえば、使用頻度が高く業務に重要な機能にはテスト密度を高めに設定し、逆にあまり使われない部分は効率化を優先して密度を下げるといった調整が考えられます。
さらに、自動化ツールの導入や、レビュー工程の強化といった施策は、初期投資が必要である一方で、長期的には大きな工数削減につながる可能性があります。これらを踏まえて、施策の効果と実行可能性のバランスを取りながら、最適な資源配分を行うことが、戦略を実行に移すうえで不可欠です。
様々なテスト戦略
あるべき姿を実現させるためのテスト戦略には、目指すものに応じて様々な種類が存在します。ここからは、代表的な6つのアプローチ法を紹介します。それぞれの特徴、メリットとデメリットを紹介していきます。
■分析的テスト戦略(リスクベース/要件ベーステスト戦略)
■系統的テスト戦略
■対処的テスト戦略(探索的/経験ベーステスト戦略)
■モデルベースドテスト戦略
■リグレッション回避テスト戦略(自動化重視のテスト戦略)
■プロセス準拠/指導ベースのテスト戦略
■分析的テスト戦略(リスクベース/要件ベーステスト戦略)
分析的テスト戦略とは、リスクや要件、過去の不具合情報、変更履歴など、プロダクトに関連する情報を分析した上で、テスト対象や優先順位を決定するアプローチです。限られたリソースの中で最大限の品質保証を目指すために、テストの「的」を絞り、重要な箇所を重点的に検証することが特徴です。以下では、分析的テスト戦略としてよく採用されるリスクベースドテストと要件ベーステスト戦略について説明します。
・リスクベースドテスト
リスクベースドテストとは、ソフトウェアの各機能やモジュールに対して「リスク値」を評価し、その値に応じてテストの優先度を調整する手法です。たとえば以下のような観点でリスクを分析します:
- 機能の重要性(ビジネスへの影響度)
- バグの発生履歴
- コードの変更頻度
- 技術的な複雑さ
高リスクと判断された部分には重点的にテストリソースを投入し、リスクの低い領域は簡易的な検証にとどめることで、効率よく品質のリスクを低減することができます。
・要件ベーステスト戦略
要件ベースのテスト戦略は、明示された要件仕様書をもとにテストケースを設計・実行するアプローチです。ユーザー要件やシステム要件をテストの基盤とすることで、「要件が満たされているかどうか」を客観的に検証できます。
この方法は以下のような特徴があります:
- 明確な仕様に基づいたテストが可能
- 要件トレーサビリティの確保が容易
- ステークホルダーに対して成果を説明しやすい
ウォーターフォール型開発など、要件が比較的安定しているプロジェクトでは、要件カバレッジを明示しながら進められる信頼性の高い手法です。
メリットとデメリット
メリット
分析的テスト戦略には、効率的にテストを進められるという大きなメリットがあります。限られた時間や人手の中でも、リスクや要件などをよく分析することで、「どこを優先してテストすべきか」をはっきりさせることができます。たとえば、不具合が起きやすそうな部分や、重要な機能に集中してテストを行うことで、効果的に品質を高めることができます。また、この戦略は、なぜその部分をテストするのかという理由を説明しやすいため、テストの管理者やステークホルダーに納得してもらいやすいという利点もあります。テストの目的が明確になり、チームの間でも認識をそろえやすくなります。
デメリット
最初にリスクや要件をしっかり調べて分析する必要があるため、準備に時間がかかるという点です。また、もしその分析が不十分だった場合、本当にテストすべき部分を見逃してしまう可能性もあります。さらに、プロジェクトの途中で仕様変更などが起きた場合、最初に立てたテストの計画を見直す必要が出てくるため、柔軟な対応がやや難しいという面もあります。
このように、分析的テスト戦略は「計画的にテストを進めたい」「優先順位をはっきりさせたい」という場面ではとても効果的ですが、正確な情報と分析力が求められるため、使う際には注意が必要です。
■系統的テスト戦略
系統的テスト戦略とは、あらかじめ決められた、ルールやテスト設計技法に従って、計画的にテストを実施するアプローチです。たとえば、同値分割法や境界値分析などの技法を使って、網羅的にテストケースを作成します。これにより、テストの抜けや漏れを防ぎ、テストカバレッジ(どれだけテストできているか)を最大化することが目的です。
この戦略では、機能に対して入力値のパターンを洗い出し、それぞれのパターンごとにテストケースを用意することで、一定の品質を保ちながらテストを進めることができます。また、事前にチェックリストや操作ルールなどを整備しておけば、テストのばらつきも減り、誰が担当しても安定した品質のテストが行えます。
系統的テスト戦略は、主に以下のような要素に基づいて進められます:
- テスト設計技法(同値分割法、境界値分析など)、事前に定められたテストケース
- 故障チェックリストや操作性に関するルール
- 社内で定められた基準やポリシー
この戦略は、高い信頼性が求められるシステム(例:金融システムや医療システム)、または複雑なロジックを持つソフトウェアに適しています。また、テスト初期段階から不確定要素を減らせるため、プロジェクト管理の負担軽減にもつながります。ただし、あらかじめ決められた基準に沿って進めるため、柔軟な対応は難しく、市場の変化や仕様の変動などには即座に対応しづらいという側面があります。
メリットとデメリット
メリット
テスト設計技法や既定のルールに基づいてテストケースを作成するため、抜け漏れの少ない網羅的なテストが可能になります。これにより、テストカバレッジが高まり、ソフトウェアの品質を確実に確認できます。また、テスト基準が明確に定義されているため、担当者による品質のばらつきを抑えることができ、チーム全体で一定水準のテストを維持しやすくなります。
さらに、チェックリストや社内ポリシーを活用することで、テスト担当者の負担を軽減できる点も利点の一つです。特に、複雑な仕様や高い信頼性が求められるシステムにおいては、この戦略が有効に機能します。
デメリット
網羅性を重視するあまり、テストケースが膨大になりやすく、準備や実行に多くの時間とコストがかかる可能性があります。また、ルールに厳密に従う特性上、急な仕様変更や市場ニーズの変化といった外部要因に柔軟に対応するのが難しいという課題もあります。
■対処的テスト戦略(探索的戦略)
対処的テスト戦略は、あらかじめ綿密な計画を立てるのではなく、テストの実施中に発生する出来事や気づきをもとに、柔軟に対応しながらテストを進めていくアプローチです。この戦略では、テストの設計や実行は事前に細かく決められておらず、実際のテスト状況に応じて臨機応変に調整されます。このようなスタイルは、特に仕様が不明確な場合や、変更が頻繁に発生するような状況において有効です。想定外の問題やリスクにもすぐ対応できるという点が特徴です。
対処的テスト戦略において重要なテスト手法の一つが「探索的テスト」です。探索的テストとは、テストを実施しながら新たな観点や疑問点を見つけ、それに応じて次のテストをその場で考えて進める方法です。この手法では、テスターの知識や経験、直感が大きく活かされます。例えば、テスト中に見つけた不具合や違和感のある挙動をきっかけに、それに関連する機能を重点的に調査する、といった進め方が可能です。事前の詳細なテストケースは用意せず、状況に応じてその都度設計していくため、柔軟で実践的なアプローチといえます。
メリットとデメリット
メリット
対処的テスト戦略の最大のメリットは、柔軟性と即応性です。仕様が未確定、あるいは変更が頻発するような開発現場において、あらかじめ決めた計画に縛られることなく、今必要なテストをその場で判断して実行できるため、効率的かつ実用的です。また、テスト実行者のスキルや観察力が活かされるため、従来の計画的なテストでは見逃されがちな不具合を発見できる可能性もあります。
デメリット
一方で、計画や記録が曖昧になりやすいため、後からテストの再現や成果の確認が難しくなるリスクがあります。また、テスターの能力に大きく依存するため、経験の浅いテスト実行者では効果が出にくい場合もあります。そのため、対処的テスト戦略は、熟練したテスト実行者が主導し、状況に応じて他の戦略と組み合わせながら活用するのが望ましいと言えるでしょう。
■モデルベースドテスト戦略
モデルベースドテスト戦略は、ソフトウェアやシステムの動作・構造・振る舞いを「モデル」として表現し、そのモデルをもとにテストを計画・設計・実行するアプローチです。
ここでの「モデル」とは、状態遷移図やフローチャート、UMLのシーケンス図など、システムの動作や仕様を図や記述で表したものです。この戦略では、作成したモデルから自動的にテストケースを生成することも可能であり、テスト設計の効率化やテストの網羅性向上が期待できます。特に、ソフトウェアの複雑な挙動を可視化しながらテスト設計を進めることで、漏れの少ない高品質なテストが可能になります。
モデルベースドテスト戦略で使われる代表的な技法には、以下のようなものがあります。
・状態遷移モデル
システムの状態と状態間の遷移を図式化し、その遷移に基づいてテストケースを作成します。たとえば、ユーザーログイン状態や画面遷移の流れなどをモデル化するのに適しています。
・信頼度成長モデル
時間の経過に伴うバグの発生数や修正状況をグラフ化し、テストの進捗や品質を評価するために使われます。
・UML(統一モデリング言語)
シーケンス図やアクティビティ図などを使い、システムの振る舞いや処理の流れをモデル化します。
・フローチャートや制御フローモデル
ロジックや処理の流れを可視化し、そこから網羅的にテスト条件を抽出します。
これらの技法を活用することで、複雑な仕様でも整理された視点からテストが行えるようになります。
メリットとデメリット
メリット
モデルベースドテスト戦略の大きなメリットは、テスト設計の効率化と高い網羅性にあります。一度モデルを作成すれば、それに基づいて多くのテストケースを自動生成できるため、設計作業にかかる時間を大幅に削減できます。また、人間の目では見逃しがちな複雑な条件やエッジケースもモデルを通じて抽出しやすくなり、テストの抜け漏れを防ぐ効果もあります。さらに、モデルを使うことでテストの自動化や保守性の向上が見込めるため、長期的なテスト運用にも適しています。特に、状態遷移の多い組み込みシステムや複雑な業務ロジックを持つソフトウェアに向いています。
デメリット
デメリットとしては、精度の高いモデルを作るための専門的なスキルや知識が必要であることが挙げられます。また、初期段階でのモデル作成には時間とコストがかかるため、小規模なプロジェクトや短期間での開発には不向きな場合もあります。とはいえ、中長期的に見れば、モデルベースドテスト戦略は品質と効率の両立を実現する有力な手法であり、再利用性や継続的改善にも貢献できる戦略です。
■リグレッション回避テスト戦略(自動化重視のテスト戦略)
リグレッション回避テスト戦略は、ソフトウェアの修正や機能追加などの変更によって、すでに動作していた機能が意図せず壊れてしまう「リグレッション(回帰不具合)」を防ぐことを目的としたテストアプローチです。この戦略では、既存機能が今までどおり正しく動作しているかを確認するために、リグレッションテストと呼ばれるテストを繰り返し実行します。特にアジャイル開発のように頻繁な変更が発生する開発スタイルでは、リグレッションのリスクが高くなるため、この戦略をとることは有効です。
メリットとデメリット
メリット
リグレッション回避テスト戦略のメリットは、既存機能の品質を維持できる点にあります。変更による影響を素早く検知し、リリース前に不具合を取り除けるため、プロジェクトの安定性や信頼性が向上します。また、自動化との相性が良く、テスト作業を効率化できるため、開発サイクルを短縮する効果も期待できます。
デメリット
デメリットとしては、既存機能を網羅するテストケース群の管理コストが高くなることが挙げられます。ソフトウェアの変更に応じてテストケースの見直しや更新が必要になるため、長期的に運用するためにはメンテナンス体制の整備が不可欠です。とはいえ、頻繁な変更が求められる現代の開発現場においては、リグレッション回避戦略は欠かせない存在です。特に、継続的な品質保証を目指すチームにとって、信頼性と効率を両立させる重要なアプローチとなるでしょう。
■プロセス準拠/指導ベースのテスト戦略
プロセス準拠/指導ベースのテスト戦略は、あらかじめ定められた外部の標準や指針をもとにテストを進めていくアプローチです。「プロセス準拠テスト戦略」は、ISO/IEC/IEEE 29119などの国際規格や業界標準に沿って、テストプロセスや手順を体系的に実施します。一方、「指導ベースのテスト戦略」は、外部の専門家やコンサルタントのアドバイスを受けて、テスト戦略やテスト計画を構築・改善していく方法です。これらは、医療機器や航空機ソフトウェアのように高い品質保証が求められる分野で採用されることが多く、テスト工程の一貫性や信頼性を確保するのに適しています。
メリットとデメリット
メリット
この戦略の主なメリットは、国際規格や業界の専門家の知見を取り入れることで、テスト品質を安定的かつ体系的に向上させられることです。定められた手順に従うことで、テストプロセスの一貫性・再現性・トレーサビリティが確保され、開発チーム全体の品質意識も高まります。また、外部監査や顧客要求に対しても説明責任を果たしやすくなるため、特に厳格な品質管理が必要なプロジェクトでは有効です。
デメリット
デメリットとしては、柔軟な対応が難しいことが挙げられます。標準や指導に厳密に従う必要があるため、プロジェクトの状況に応じて臨機応変にテスト方針を変えることが難しくなる場合があります。さらに、外部指導を受ける際にはコンサルティング費用や教育コストが発生する点にも注意が必要です。とはいえ、一定の品質基準を確実に満たしたいチームや、テストプロセスを組織的に整備したい状態であれば、この戦略は非常に有効な選択肢となります。
テスト戦略をたてる時のポイント
テスト戦略は、プロジェクトの品質と成功を左右する極めて重要な要素です。プロジェクト全体の目的やリスクを把握したうえで、現場に即した現実的な戦略を立案・運用していく必要があります。誤った戦略を選択すれば、品質低下やスケジュール遅延、予算超過といった致命的な失敗を招く恐れがあります。以下では、テスト戦略をたてる際に覚えておきたいポイントを5つ紹介します。
実現性のある戦略を立てる
テスト戦略では、理想論に偏るのではなく、プロジェクトやチームの実情を考慮し、「実現可能な戦略」を策定することが不可欠です。たとえば、指導ベースの戦略を構想していたものの、スケジュールや予算の都合で外部専門家を招くことが困難になるなど、理想と現実にギャップが生じることがあります。そうした場合、戦略自体が頓挫してしまうリスクがあります。そのため、事前にチームのスキル・リソース・予算状況を把握し、「今のプロジェクトで本当に実行可能な方針かどうか」を冷静に見極めたうえで戦略を構築する必要があります。
早期からテスト工程を見据え、情報収集に努める
効果的なテスト戦略を実現するためには、プロジェクトの初期段階からテスト担当者が積極的に関与し、必要な情報を徹底的に収集することが重要です。要件定義や基本設計の段階からテスト担当者が参加することで、仕様の曖昧さや矛盾点を早期に発見でき、テスト計画への反映が可能になります。仕様の曖昧な点や矛盾点を発見できれば、手戻りを大幅に削減できます。また、開発チームやプロダクトオーナーとの対話を通じて、重要な機能やユーザー利用状況の把握に努めることも、テストの優先順位付けを効果的なものにすることができます。情報収集は単なるドキュメント確認ではなく、開発意図やリスク、背景までを深く理解するための「対話と観察」を伴う行動として捉えるべきです。このようにすれば、テストの精度を高めるだけでなく、開発プロセス全体のスムーズな連携を促進し、品質を高めることに役立ちます。
リスクベースの優先順位付け
現実的なテスト戦略には、リスクを軸とした優先順位付けが不可欠です。すべての機能を均等にテストすることは、現実的には不可能であり、限られた時間とリソースをどこに投入するかを明確にする必要があります。特に、新たに追加した機能とそれに影響をうける既存部分・過去に不具合が多発したモジュール・セキュリティに関わる機能といったリスクの高い範囲を特定し、重点的にテストを実施することが、限られたリソースを最大限活用することにつながります。このリスクを軸とした考え方は、テスト戦略全体にわたって反映されているべきです。これにより、重要な不具合を早期に発見することが可能になります。
柔軟性と継続的改善の姿勢
テスト戦略は、一度策定したら終わりではなく、状況に応じて柔軟に見直し・改善を繰り返していくべきです。開発が進行する中で、仕様変更、リソースの変動、新たなリスクの出現など、さまざまな変化が起こりえます。そうした変化に対応できなければ、戦略はすぐ形骸化してしまいます。また、プロジェクト終了後には必ず振り返りを行い、「戦略はどこまで有効だったか」「改善すべき点は何か」といった観点からレビューを実施し、ナレッジとして蓄積・共有すれば、次回以降の戦略精度向上に繋がります。
ナレッジの蓄積とテスト教育の推進
効果的なテスト戦略の運用には、テストから得た成果の蓄積と、それを活かせる体制づくりが欠かせません。たとえば、バグ発生傾向や過去のテスト結果の分析は、今後の分析的テスト戦略の精度向上に役立ちます。また、テスト戦略の実行には、現場の担当者がその戦略を正しく理解し、実行できる能力を備えている必要があります。そのため、テスト戦略の策定者だけでなく、実行メンバー全体への教育・トレーニングを継続的に推進することも、長期的な品質向上において重要な要素となります。
まとめ
テスト戦略とは、品質を確保するためにテスト全体の方針や優先順位、実施方法を定める指針であり、プロジェクトの初期に策定されます。変化の大きいIT業界では、有効な戦略をたてていなければ変化に対応できません。テスト戦略を立てるには、まず組織やプロジェクトのあるべき姿を明確にし、プロジェクトでの現実的な目標を設定します。
そのうえで目標達成のためのアプローチを選定し、課題の分析を通じて施策を具体化します。さらに個別戦略を策定し、限られたリソースを効果的に配分します。テスト戦略とテスト計画は密接に連携し、品質と効率を両立させるために両者を適切に設計・運用することが求められます。実現したい内容によって、採択されるテスト戦略は異なります。有効なテスト戦略を選び、場合によっては、変更しつつ、業界の変化に対応していくことが求められています。
